月一で行われるわけではないので、並行してお聞きしている訳ではないのですが、宗匠から日本の神々についてのお話を伺うのと同様に、お坊様から仏教についてのお話を聞かせていただいておりまして。
仏教というのは布教してはいけない教えなのだそうですね。
「どんな素晴らしいご馳走でもお腹いっぱいの時に出されたら苦痛。どんな素晴らしい教えでも求められない時に伝えたら、その素晴らしさを受け取れない。それはその教えの価値を損なうことになる」
というのが、その理由。仏教というのは基本教えを受けたい側が
「教えてください」
と教えを授ける側にお願いしなければ伝えてもらえないそうなのですね。世の中には、頼まれなくても教えたくて仕方がない方々もおりますが、これを知っていると仏教系に限って言えば、少し困った方々を避けることが出来ますね。
(お坊さんから話を聞いたことはあるけれど、自分から頼んだ覚えがないという方々はご自身の代わりに別の誰かが頼まれたのでしょう。「薬師寺のお坊さんのお話は面白かった」と修学旅行の思い出を語る方は多いですね)
神の話を聞き、仏の話を聞くと、この国で暮らす人々が神と仏に何を祈ってきたのか、どのようにこの国の歴史を織りあげって言ったのか、通り過ぎていった数多の名のない人々、歴史に名を遺した人々の影を残されたものの姿から見えるような気がいたします。
目に見える形を纏う御仏に人々はどのように祈りを捧げたのか。目に見えぬ姿でおわす神々に人々はどのように加護を乞うたのか。
何故人々は神仏に水を捧げ、花を捧げ、香を焚いて祈ったのか。
仏教において、御仏に渡すことの可能な供物は香りだけ。御仏と亡き人々を持て成す為に、捧げる為に、より良き香りを求めて、貴人は金より貴重な香を焚き、貧者はなけなしの金を握り締めて一本の香を焚く。
仏教は祈る。いつか、この世界が変わることを。六道輪廻。生きることは修羅。人も動物。動物であるからには生きる為には他者をも喰らう。喰われない為なら殺す。
自らが生き残る為ならば謀略も張り巡らす。生きものである以上、生存競争からは逃れられない。
動物は人とは違う?そんなものは自分の思想に溺れて、動植物の生態を見ようとしないもの達の幻想。
生きとし生きるものは全て、それぞれの生存戦略を選んで生き延びる為の策をめぐらす。
それは命あるものの性。
私達は、自分を、家族を、故郷を、国を、大事なものを守る為なら躊躇いもなく手を汚す。動物は縄張り争いをするようになっている。自分のテリトリーを侵すものには、怒りを感じるようになっている。
自分のテリトリーを侵すものを許すことは、自分の餌場を奪うことを許すこと。生き延びる為には譲れないこと。
自分を守る為に天から与えられた感覚。私達に与えられた必要悪。この我執からどれだけ自由になれるか。
王子という恵まれた地位を捨て、美しい妻と可愛い子供を捨て、それでも仏陀が追い求めたもの。
釈迦牟尼の時代から数多の人達が繰り返し挑戦し、未だ達成できないもの。それでも願い求め続けられてきたもの。
それが、どんなに難しいことは白河法皇の言葉で分かる。
「賀茂川の水、双六の賽、山法師。これぞ我が心にかなはぬもの」
仏法を護る僧侶でさえも、武力で自分達を守ってきた。仏法に従う為に、武力で自分達を守ることを良しとしないチベット僧達は暴力によって弾圧を受けてきた。
動物は我執に興味を持たない。己が生きることしか考えないものには、その結果起こることは見えない。
見えないから変わらない。見えないから気づかない。気づきを促す為に水を振りかける。
流れゆく汚れが何なのか、何故ついたのか、己を見つめさせることで根本の原因に目を向けさせる。原因があるから結果がある。そういうことが起こる条件が整ったから、そういうことが起こる。
良い因果が回るように。良い気づきが得られるように、僧侶達は仏に祈る。
では、神とはいったい何だろう?日本の神とはいったい何だろう?
神とは人心の仮託。今期の講座で宗匠は繰り返し、そう話されました。「政治」と書いて「まつりごと」、「祭祀」と書いて「まつりごと」
神と政治が結びつくのは日本特有の話ではない。メソポタニアでもエジプトでも祭祀は政治と結びつく。
人の力では、どうにもならないことに対して神を求めるのが人に与えられた性なれば、その性を政に利用しようと考えるのは為政者なれば当然のこと。
宗匠は語られる。神とか何か?日本の神様とは何か?その問いに対して語られる。神様とは弁だと。バルブだと。
弁が正常に動くから心臓が正常に動く。生まれつき弁に異常のある子供は手術出来る年齢に達するまで運動が制限することもある。
身体の健やかさを保つ為には血液が適切に流れることが必要。流れは滞ってはいけない。流れは逆流してはいけない。心臓がポンプとして適切な役割を果たさなければ、身体は動かず、脳にも支障が出る。
神とは人心の仮託。ところが人心をそのままの形でもっていくと物事が動かない。人心には、ベクトルがある。一人の人の心の中でさえも、同時期に様々な方向へ心は動く。
願ってはいけないと分かっていることを願う。やってはいけないと分かっていることをやる。
人の心は悍馬のよう。轡をはめておかなければ、自身でさえも制御できない時もある。
様々な方向へ走り出そうとする悍馬をまとめあげ、目指す方向へ走らせるには馭者が必要。
暴れ川から取水し、過剰でもなく過少でもなく、必要な量だけの水を地に行き渡らせるには弁が必要。
このバルブを日本人は神にしてきた。これが一神教の国々と多神教である日本の神との大いなる違い。
人心があるからバルブが必要。人の心の流れを調整するには弁が必要。人の心は目に見えないもの。だから見えるようにした。
神という形で人の心を調整するバルブを目に見えるようにした。
西の地の神には名前がない。一神教の神には名前がない。「全地をしろしめすいと高き者」「崇め祀られるもの」と称号で呼ばれるだけで名前がない。
日本の神には名前しかない。日本の神は姿を持たない。教会で磔刑にされるキリスト像のように見える形で現れない。
神像でさえ、海を越えて仏がやって来るまでは存在しなかった。仏教が仏像を持ち込んだことで、仏像を真似て神像がつくられた。
仏の像があるならば、神の像もないとおかしいだろう。ただ、それだけの理由で神像も作られた。
日本の神は、その姿を確かめる為の像など必要としなかった。姿は、どこにも見えぬとも神は確かにおわします。
日本の神は、見るものではなく聞くもの。見える形ではなく、聞こえる形で存在している。この音、神の名を顕わす音が人心制御の為のバルブ。
遠い、遠い地から、人類発祥の地であるアフリカから太陽を求め、自分達に安全と安心をもたらす東から昇る輝くものを求めて、東へ東へと旅を進めて、海を渡り、極東の島国まで辿りついた。
皆、太陽が欲しかった。手に入らぬものを求めて大陸の果てまで来た。そこでも望みは叶わず、この海を越えればあるという島国ならばと海を渡り、そして長い旅路の果てにたどり着いた場所でも太陽は手に入らず、それ以上先に旅を続けることが出来ないと悟った。
どこまでも続く大海原。太陽を得るという望みを捨てずに飛び込むか。このまま、あてどない旅を続けるか。
人々は、その問いに神という答えを作った。アマテラスという名で人の心を制御した。アマテラスというバルブを作ることで海へ飛び込もうとする足を止めた。
「アマテラス様が、ここに留まれとおっしゃられた」
そう告げることで、海へ飛び込もうとした人々は飛び込むことが出来なくなる。太陽が手に入らないのなら、夜空を照らす月が欲しい。
そう願う人々も神の名を用いて、こう返されれば納得せざるをえなくなる。
「ツクヨミ様が此処にいたいとおおせになった」
皆が欲しかった。皆が自分のものにしたかった。けれど神の名前で
「ツクヨミ様が、そうお望みだ」
と返されれば、矛を収めざるをえなくなる。月を得る事を諦め、月は天にあるものと見ているだけで済む。
神の名前はバルブ。そして神こそがバルブ。人心をどのベクトルに向かわせ、どの量で、どのスピードで向かわせるかという機能。
これが神様。日本という国の神々。見えないもの。名前という音しかないもの。けれど、その音を聴けば、その神様の存在を皆が分かるもの。
神様の名前を知っているということは、その神の存在を受け入れた、あるいは確認したということに他ならない。
「神って何?」と追究し始めたら一神教。西洋人は「神って何?」と追究することで哲学を伸ばしてきた。
けれど日本人には、そういう形での哲学はない。「神さまって何の?」日本人にとって、神は追究するものではない。
どの神様なのか?何の神様なのか?日本人にとっての関心はそれ。まったく次元の違うこと。まったく違う地面から生まれる比べられない問い。
「神って何?」その問いを発したものが日本でもいなかったわけではない。けれど、それは少数派。「あの人は変わってるからねえ」と容認される程度の存在。
「神って何?って。これは火の神様だろう」
そう答える方が多数派。置かれている環境が、それぞれが発する言葉を生み出す。
人心とは、坂道を転がる石、川を下っていく水と同じ。同じくらい止められない。多神教の国と一神教の国。
置かれている環境も人心の掌握の容易さも異なる。欧州の歴史は戦乱の歴史。外敵から身を守る為、街は城壁で囲まれている。
城壁の中にいるものは租税と引き換えに安全を得る。どんなに為政者に不満があろうとも、民は城壁の中にいるか、城壁の外にいるかの違いは理解している。
固い壁の中で守られた民。街を囲む城壁が人心の掌握を助ける。街を囲む城壁は、東洋と西洋の哲学の在り方も分かつ。
一つの哲学が生まれた時、城壁に囲まれた都市の中ではその考えが広まるのも容易い。
「神とは何か?」解けない命題が与えられると、城壁都市の中で議論が始まる。
それぞれが己が考えた答えを示し、それが妥当か論理的に瑕疵がないのか精査され、議論の対立が思考を深める。
我が国は「神とは何か?」と考えていられるような場所はない。「神とは何か?」を考える前に災害によって引き起こされたこと、災害によって引き起こされる被害を少なくするよう備えておくことを片付けておかなければならない。
外敵から身を守る為に固い城壁で守られている訳でもないので、人の心も勝手に動く。為政者の頭を悩ませる事件も多発する。
神様なんて考えているより、目の前のことを解決する方に力点が置かれるのは自然なこと。従って、一神教は育たない。
「神とは何か?」と考えるものはいた。けれど、それは村人全部、そのくに全部、日本中全部を惹きつけられるような大きな問いにはならなかった。
他にも大事なことがあり過ぎた。
では、この纏まらない人々をどうやってまとめあげ統治していくか。その方法を考えたのがアマテラスの寵臣。祇侯神である天児屋。
この神が人心操作をするという人心を作った。神というバルブを使ったら、人心という暴れ川を暴走させることなく管理できることを見出した。
人の心が少しばかり拙い方向に動いたら、そちらに水が流れないようバルブを調整すればいい。
「今は、その神様は流行ってないよ」
「今、お詣りに行くとしたら宗像の神様でしょう」
「天手力男の神のご利益が有難いって!」
「武運を祈るなら、やっぱり八幡様だ」
神というバルブが人の心を摑まえる。人心を調節する為にスサノオ神も二つに分ける。天王と祇園というバルブを作り、スサノオのそれぞれの面に従う人々を作る。
そのようなことが出来るようにバルブの役割を神に仮託した。一神教だったらバルブは一つでいい。神の愛、それだけで人を従わせることが出来る。
神の愛による保護と、神の保護下から外れることの恐怖が人の心を神に従わせる。
多神教の国では、神の愛だけでは人の心は掴めない。そんなに神様が愛してくれるなら、何故この間の台風でうちの田の畔は壊れるんだ?
神の愛では壊れた畔を直した時に痛めた腰は治らない。神の愛よりも
「腰痛めなら、あそこの神社に行くといいよ。あそこの神様は腰痛にご利益あるから」
という言葉の方が大事。あそこの咳封じ。あそこの神様の護符は腰痛に効く。そういう話を聞けば、どんな遠方でも出かけていって手を合わせる。
西洋だって、そこを詣でれば、どんな病に効くという泉はある。でもそれは泉の力。神の愛が治したわけではない。
聖母が泉のことを助言してくれたという伝説はあるが、聖母の助言を神の愛とは呼ばないだろう。
痛みも神が与えたもうたもの。苦しみに耐えることも神への愛の証。日本人には、この感覚は腑に落ちない。愛があったって痛みは痛み。痛みに何もしてくれない神様よりも、痛みを取るというご利益を与えてくれる神様の方が有難い。
神様の名前を聞くだけで、人心の方向や形や強さ、こういったものを制御できるという多神教の良さ。これが日本にちょうど良かった。
国体というものを考えるのに、ちょうど良かった。だから日本人は多様性というものを受け入れることを何回もする。
多様性を受け入れるということは、バルブを沢山つけるということに他ならない。全ての事柄がバルブで制御できるわけでもない。
富士山は噴火する。地震は起こる。台風は木々をなぎ倒し、水害を起こす。火事は築いてきたものを、あっという間に燃えつくす。
四六時中何かが起こる。こういう多様性を受け入れる為にも、呆然とした後、再び動き出す為にも沢山のバルブが必要となる。
引き起こされたことによって起こる、全ての人心を制御するバルブ。これが神の名前とした。神の名前を聞くだけで人が動く。
「そこは水の神様がいる時期なんだから、こんな時に行くもんじゃないよ」
「厠にも神様がいるんだから、ちゃんと綺麗にしておきなさい」
「お伊勢様の御札が降ってきた。これは伊勢にお詣りにい行かないと」
神様の名前一つで人は動く。やろうとしていたことを止めたり、やらなければと思ったり、何が何でもそうしなければと全ての理屈をねじ伏せて動いたり。
これ全て、神の名前が引き起こしたこと。
「お伊勢様の御札を見たんです」
この言葉だけで、ひしゃく一つで旅に行ける。それを聞いた人は
「ああ、では私は行けないから私の代わりに拝んでください」
その言葉だけで、その旅を手助けする。通信の手段が手紙と言葉しかない時代。それを可能にした名前の威力。
木と気、どちらも同じ「き」という音を使う。違いは目に見えるか見えないか。気と木と紀。どれも同じ音を使う。「紀」は書かれているもの。目に見えるものを指す。
幸運なことに日本人は「木」を見る機会が多かった。建物も道具も什器も木で作られるものがほとんどだった。
石で作られたものもあったが縄文時代には、すでに木か陶器(とうのき)しかなかった。
木を見る機会が多かったので、「木」を「き」と呼んだ。
木も気も紀も日本人は「き」と呼んだ。もっとも、この三つの文字のうち「気」は漢字が来てから「き」という言葉になったと推測されるが、三つとも同じ「き」であることは間違いがない。
音の持つ意味が同じものを日本人は「き」と呼んだ。では「き」とはいったい何だろう?一番古い言葉は木。日本人は木に畏怖を感じた。
地面からいきなり太いものが生え、それが空に向かって見上げるほど高く伸びてゆく。
見た目は背が高くて、一本ボンと生えていて、ボンと生えた後先に向かって細かくなってく。上にいけばいくほど、幹は細くなり、枝がでてゆく。
下から途中までは一本の木なのに、そこから先は細かく枝分かれして、桜などはその細かく分かれた枝から沢山の花を咲かせる。
木の構造を知らない古代の人々にとっては不可思議な存在。
なので根幹は一本なのに、先端は分かれている。これをまず「き」とした。太い幹から始まり、広がるもの。
木は、切り倒し、板にした後も不可思議なことが起こる。板の木口の方に水を落としたらあっという間に無くなる。なのに板目に置いたら、長い時間水は残る。
同じ木なのに、切り口によって水の吸われ方が違う。当時の人々にとって、その違いが不可思議であったけれど、人間の頭の弁を使うことによって、すぐに切り替えられた。
「こちら側を使えば、水を保っていられる」
逆に言えば、木口を使えば、水気を取りたいものからどんどん水を吸い取ってくれる。こういうものを見て、古代の人々はこれを「き」だと思った。
木と気は変わらない。日本語は言霊ではなく音霊の国。単語を形成する音の一つ一つに単語に則した音の意味があり、則した音を組み合わせるから、その単語の意味となっていく。
菓子という単語は「か」と「し」の音に意味があるから、「かし」という単語になる。
日本語は、祝詞。意味ある音を組み合わせて作られている。
「き」怖くて、不思議で変わったものを指す音。春になれば花が咲き、夏になれば葉を広げ、秋になったら葉の色を赤く染めて落し、冬にはまだ骨だけになる。
動いていないのに、動いている。これは「神」だと、ある時人は思う。人々は「木」に天之御中主を、古事記の中で一番最初に登場する神を見た。
だから漢字が海を渡ってやって来た時、「気」の文字が来た時に「き」の音を使った。「気」は大陸から渡ってきた時は「け」と呼ばれた。
ところが気という字を使い続けているうちに「気」は「き」と呼ばれるようになった。それは「気」が「木」に似ているから。
「木」は目に見えるもの。「気」は目に見えないもの。いったいどこが似ているというのだろう?
元気、気づく、気が気でない。全て目で見えないもの。ただし、それは全部先が割れているものだと日本人は考えた。先がぼんやりしているもの。それは「き」。
木の幹は木に近づけば見える。けれど、いくら目をこらしても見、上げた木の先端は見えない。
離れたところから見つめれば、木の全体は見える。見えるけれども、ぼやっとしている。太い幹ははっきり見えても、幹から広がった枝の先は細かく分かれていて、どうなっているかはっきり見えない。先が、ぼうっとしたものが「き」。
元気は目に見えるか?気づくは、気の何で認識した?すぐ傍にいて、元気に話している声を聴けば、今日も元気そうだなと思う。
そう思った相手から、300メートル離れた時、元気か否かを判断できるか?先が、ぼーっとしているものが「気」。
「木」の先はぼうっとしている。「気」は「木」に似ていると日本人は考えた。「け」だったのに「き」にしてしまった。
「き」は先がぼうっとしている。これを神だと考えた。とても不思議なものを神だと考えた。
木には股がある。根から吸い上げられた水が、どちらの股を通って樹上に上がっていくか。インクで染めた水を吸わせ、どのように木が水を吸い上げるか実験してみても、水は均一に吸いあがらないということは分かっても、では何故?という不思議は残る。
枝葉が多い方につながる木の股がより多く水を吸い上げる。それは分かる。では、何故?
分からないから怖い。理由が想像できないから怖い。
木の木口は水を吸うということは分かっていた。木の板には、水を吸う面と吸わない面があることが分かった。
分かったら、「何故?」というその理由を研究していったのが西洋。「神はなんだ?」という一つのことを追求して考えるという哲学を持っているのが西洋。
これも神だろうか?と研究していき、これは神ではない。このような自然現象の結果起こったことである、と木の生態を解きほぐしていくのが西洋。
日本人の向き合い方は違う。木には神様がいると思った。気の先、木の先端の葉の多いぼわっとしたところに神様がいると思った。神様が水を吸っていると思った。だから枝葉が多い方につながる木の股がよりも多く水を吸い上げると考えた。
枝葉が多い方につながる木の股がよりも多く水を吸い上げる。その事実は分かった。けれど理由が分からない。
理由が分からないのは怖い。怖いからなんとか理由を知ろうとする。より多くの水を吸い上げるその力。それが何かが分からない。分からないその力に名前をつける。「これも『気(き)』にしよう。」これが日本人の向き合い方。
木を怖がったのは日本人だけではない。世界共通で古代の人々が、その在り方を不思議に思い、理解できないものとして恐怖を感じたのは木。けれど日本人は木に対して恐れではなく、畏れを感じた。
どんどん言葉を作ったり、どんどん道具を作ったりしていくと怖いものは増えていく。全てのものに怖れを覚える。
知らないものは怖い。分からないものは怖い。日本の言葉は怖いものを、神様にすることによって術中に入れる。これも弁。
怖いか、怖くないかの指針として、名前をつける、という弁を作った。名前がついているものは怖いものではなく、畏れるもの。名前のない神様は日本には存在しない。
日本の神様には全て名前がある。真実の名前。真名がある。まなとは「赤い、強い、存在」その対義語が仮名。
日本の神様には、全て真名がある。名前をつけることによって弁にした。西洋の神には名前がない。神という称号しかない。
日本の神には全て名前がある。天児屋がこのシステムを作った。日本人の恐怖心、恐れを名前をつけることによって克服し、畏怖させた。
名前をつけることによって、弁が出来る。方向性を作ることが出来る。
ここまでで神様の存在が弁だということが分かった。今まで日本人が大切にしてきたもの、それは国体。国体の本分は、八紘一宇という言葉に他ならない。
そしてそれを守っている神勅が天壌無窮の神勅。
八紘一宇という言葉はねじ曲がって伝えられている。本来の意味は
「八本の紐。全ての考えや民族は一つの空を持っている」
「世界は一家、人類は皆兄弟。森羅万象は一つの天しかない」という考え方。地球上は空が一つであるという意味。
天壌無窮の神勅は、天照大御神が天孫降臨の時に神武天皇に授けた神勅。
「貴方の子孫がこの国を治めたのだったら、一生困らないように護ってあげよう」
と約束してくれた神勅。この二つが国体という。その国体の体現者が天皇であると今から70年前までは全ての日本人が思っていた。
何故ならば、天皇が君主であったから。世界は日本だけであったから。けれど大東亜戦争、第二次世界大戦によって、世界は日本だけではないということが分かった。
日本中の津々浦々まで世界は日本だけではないことが分かった。上つ方々は、平安時代には、よその国があることは知っていた。よその国にも天がいることを知っていた。
けれど上つ方ではないものは、天皇様以外の天があることは知らない。世界には幾つも天があることを知らない。知らないので天皇様のことを、一天万乗の君と呼んだ。私達の上には天皇様がいる。すなわち国体とは天皇のことである、と日本の軍部が国体を天皇ということにした。
だから曲解されて、天皇の為に死んでいく、天皇陛下の為に何かをするという非常に原理的な方向に進まざるをえなかった。
けれど、令和、平成、昭和、三代の元号を担った方々はこうおっしゃる。
「国民こそが天である」
我々は、国民をもって天という。すなわち、天皇家というのは、ずっと
「自分達が祭祀をしをていれば、天である国民が八紘をまとめてくださる」
そう考えた。国体が天皇だというのは曲解。担う側の私達が考えたことであって、担われる側の天皇が考えたことではない。
従って、国体とはすなわち、我が国民ということになる。日本国ということになる。
私達日本国民は、日本のことを考える時に日本人が同じように見ている天というのは国民のことであると考える。
この国は弁があり、弁は神だと宗匠はおっしゃられた。すなわち、名前がついているというのが八百万の神である、ということになる。
結論から言うとあって、神とは私達。名前がついている私達。これが多神教の在り方。そして私達の国体。
これを護っていらっしゃられる。これを年に24回、細かいものまで数えれば48回拝んでくださっているのが天皇陛下。
天神地祇を祀っているというのは、すなわち国民のベクトルを祀ってくださっている。
毎年毎年11月になると天皇家は新嘗祭を行う。新嘗祭とは、国民に安んじて全からく食事が渡るように。
神に、全からく食べものが渡るようにと祈り、渡る為の作物が出来たことに感謝をあげているということ。
神様にあげているとは、すなわち私達にあげているということに他ならない。かつて三波春夫は口にした。
「お客様は神様です」
神に向き合うように、お客様に向き合う。私達は全員が神様。そして、それを制御するものを必要としたので、示す編に申すという字をつけて神。
私達の名前は戸籍に載っている。戸籍は紙。弁は示す編に申す。国民は糸編に氏。
祝詞は、神様が神様を祀る。私達があるから神があるのであって、神があるから私達があるのではない。
人心の動かなったもの。これは神になりえない。今でもあらゆる新しい事象がどんどん生まれる。けれど神になるのは、その一部。
何故ならば、私達が思っている神というのは弁であるから。けれど本当は名前がついたなら、全部が神様ということに他ならない。
日本語というのはそれを許す言語。それを肯定する言語。音読みと訓読みが存在する言語。
何回も何回も多様性を試みることによって、失敗を繰り返すことによって、言葉がどんどん増えていくことを許容し、そしてそれを理解できるベクトルと複雑なコンピュータを得た言語。
名前ということ知って、神にすることを知っている為に成し得た技を持つ言葉。それが私達の国の言葉。
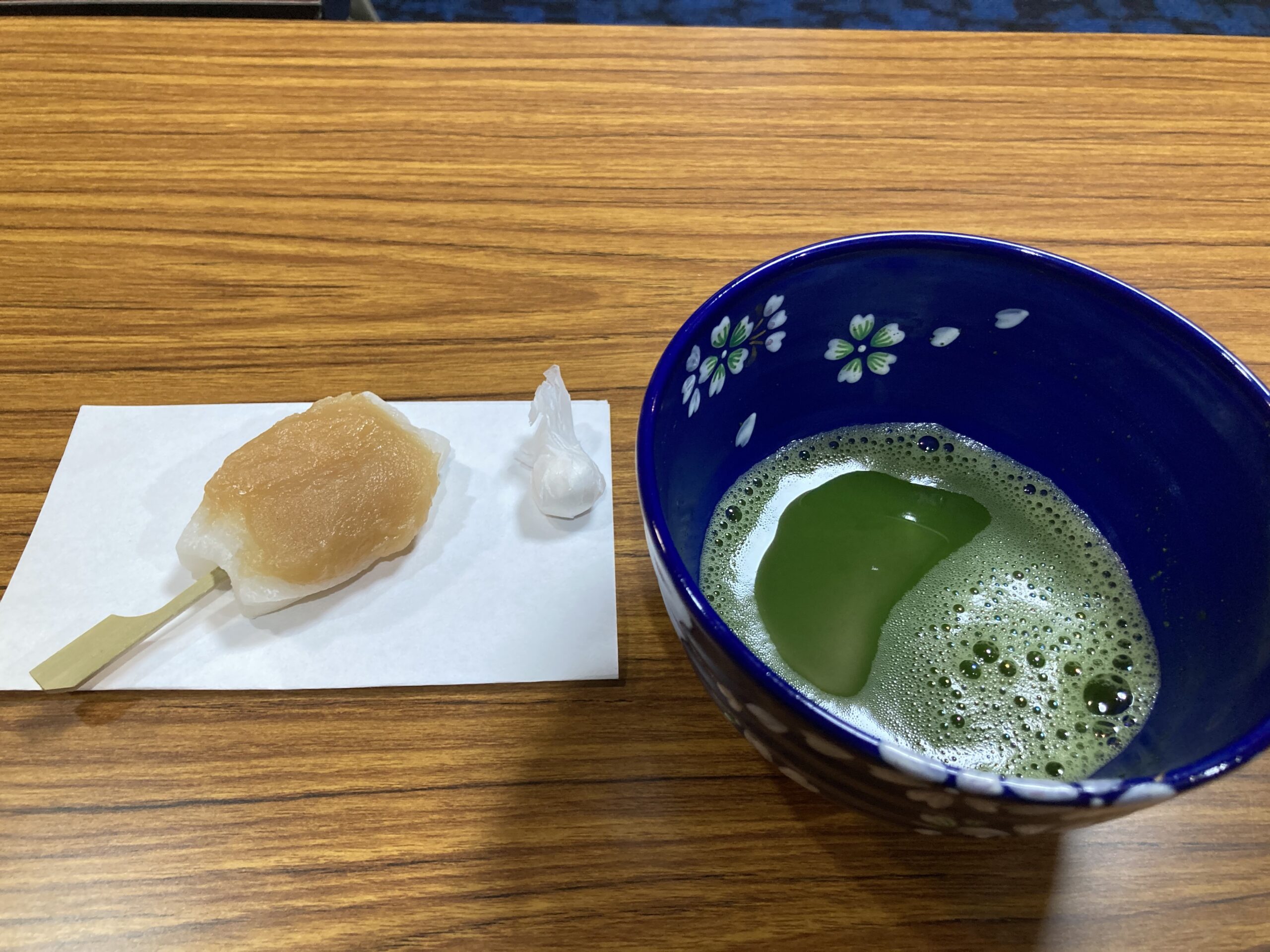
コメント